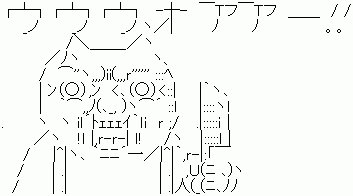はじめに
こんにちは。橙田千尋(とうだちひろ)です。自分のブログで自己紹介をしたり、普段の記事と違ってですます調で書いていると、なんだか自分の部屋でよそ行きの服を着ているような気持ちになります。
『短歌の日大賞・毎日選評2025』について、4/24のテーマ詠である「自転車」に関する短歌の選評を行いました。詳細は以下の通りです。
- 特選1首、入選2首、佳作3首を選んでいます
- 入選・佳作としてピックアップした短歌は順不同です
- ピックアップ時は短歌だけを読み、コメントや作者名は伏せました
- 敬称略です
【特選】
向こうからおでこ近づく向こうから見ればわたしもおでこ自転車/後藤たり
今回たくさんの自転車の歌を読んだ中で、最終的に「おでこ自転車」が記憶に残りつづけたように思います。語感の良さに加えてこのフレーズには、絵本に出てくるキャラクターを思わせるようなユーモラスさがあります。
「自転車」同士ですれ違うときの歌だと読みました。「向こうから」誰かが近づいてきて、「おでこ」に視線が置かれる。三句・四句で相手の視線が想像され、結句で相手と「わたし」がどちらも「自転車」に乗っていたことが明かされる。この語順も面白かったです。
人間を構成するパーツの割合として「おでこ」はそれほど大きくありません。それでも、歌に出てくる人物の中ではおでこが印象に残っているようです。相手のパーツのうち印象的な箇所だけが残り、それが「自転車」と組み合わさることでキャラクター性の獲得まで到達できるのだなと、この歌を読んでいて思いました。
【入選】
自転車でこけた私のすぐ横を通っていった車の赤さ/せんぱい
様々な状況を引き連れてくる「赤さ」という単語が、歌の魅力を支えていると感じました。
歩いて転ぶよりも、「自転車」で転ぶほうがより痛そうです。怪我の具合が深刻すぎると、その印象だけで歌が止まりそうですが、この歌では「こけた」を使うことで読み手に必要以上の深刻さを与えずに三句以降を読み進められるように思います。
歌を読む限り、「自転車でこけた私」に気づいた人はいたとしても、声をかけた人はいなかったように思います。私を気にかけずに「すぐ横を通って」いく「車の赤さ」は、「こけた」ことで負ったであろう傷の赤さや、道端で「こけて」しまったことによる恥ずかしさを同時に想起させます。そういった様々な「赤さ」を、通った車の色だけでこちらに伝えてくるところがこの歌の魅力的な部分だと感じています。
前カゴのゲームボーイが跳びはねて夏休みって全然ながい/きいろい
2つの異なる時間の長さが重なっていくところが印象に残りました。
自転車の「前カゴ」は不安定なのになぜか精密機器を入れがちです。歌に出てくる人物も、精密機器を入れているという意識が薄いからか「ゲームボーイが跳びはねて」います。上句ではこの跳びはねた瞬間が切り取られています。
対して下句では、「ゲームボーイ」が跳びはねる瞬間を包むように幼い頃の夏休みの果てしなさが詠われています。2つの異なる時間が重なることで、瞬間と果てしなさの両方を味わうことができました。
子どもの頃の夏休みは確かに「全然ながい」ですね。大人になってからと比べて中身も詰まっている気がします。「全然ながい」というフレーズによって、短い夏休みを知った現在が入り込むような印象も受けました。
【佳作】
わたくしがわたくしの帆を揚ぐるとき駐輪場のひだまり静か/有為
「わたくしがわたくしの帆を揚ぐる」という表現が魅力的でした。
上句の意味を取るのに少し時間を要しましたが、自転車で上半身が伸びるような体勢をとっていると解釈しました。上半身が「帆」に喩えられることで、伸び上がる体の様子だけでなく、身体が受けている風まで想像させるところが面白いと思います。
下句の「ひだまり静か」も、自分以外誰もいない駐輪場に陽がさしている様子を思い起こさせてくれます。個人的に、静けさを帯びているものは涼しい/冷たいものが多いような気がしています。しかし歌の中の情景がはっきりと浮かぶため、確かにひだまりも静けさを帯びているよなと認識することができました。
前カゴに花をのせればあなたへと駆ける花瓶に変わる自転車/もりなこ
歌から想像できるスピード感と、「花瓶」が「自転車」に変わるという言い切りの強さが相乗効果を生んでいるように感じました。
「花瓶」は多くの場合、安定した場所に置かれます。また、水を入れることもあるので漏れ出さないような材質になっています。対して「前カゴ」は地面の形状によって揺れますし、水は漏れるので「花瓶」からは遠いもののように思えます。
それでも「花をのせれば」「花瓶に変わる」と言い切る。その強さに「駆ける」がもたらすスピード感が合わさって、読んでいて「自転車」は「花瓶に変わる」んだなと納得させられました。韻律もスピード感を損なわない形で歌に味方していると思います。
自転車で日ごと遠くへこぎゆけば父の目を見て話せなくなる/山口絢子
「自転車で日ごと遠くへ」行くようになることと、「父の目を見て話せなくなる」こと。この二つが接続されるところに面白さを感じました。
成長するにつれ、行動範囲は広がります。遠くへ出かけることで気分が高まる感覚は、自分にも覚えがあります。しかしどんなに遠くへ行っても、自宅に戻り家族とコミュニケーションをとることになりますし、鬱陶しさを感じるようにもなります。
歌の中に出てくる二つの状況は、直接的な関係を持ちません。しかしポジティブ/ネガティブな感情を生み出す状況が歌の中で接続されることで、思春期・反抗期に起こる心の揺らぎが、歌の中で表現されているように思いました。
終わりに
以上が今回取り上げた6首になります。自転車に関する歌をたくさん読んでいくと、詠みたくなる状況や光景に関する大まかな傾向が分かって面白かったです。
たくさんの短歌を投稿してくださり、ありがとうございました。